※本ページはプロモーションが含まれています。
アブラムシは家庭菜園やガーデニングにおいて、特に注意が必要な害虫のひとつです。「アブラムシの好む植物」について知りたい方の多くは、植物に付く虫の正体や対策について悩んでいるのではないでしょうか。
この記事では、アブラムシがつく野菜やアブラムシが好む花を中心に、どこにいるのか、どこからくるのかといった基本情報を詳しく解説します。
さらに、知らないうちに進行する被害や植物への影響、大量発生の前兆についても取り上げ、アブラムシの発生を未然に防ぐための発生予防や予防方法を紹介します。
日常の手入れでできる駆除の簡単な方法から、駆除でコーヒーを使った対策が出来るのか?という疑問、アブラムシが嫌う植物の活用法と幅広く実践的な内容をお届けします。
また、アブラムシが死滅する温度や、効果的なおすすめ薬剤についても触れ、初心者の方でもすぐに実践できるようわかりやすくまとめました。植物を守りたいすべての方へ、役立つ情報が満載です。
この記事で知る事が出来る内容
- アブラムシが好む野菜や花の種類
- アブラムシの生態や発生しやすい環境
- アブラムシの発生予防や駆除の具体的な方法
- アブラムシによる植物への被害とその影響
アブラムシが好む植物の特徴とアブラムシの生態・どこからやって来るか

アブラムシが好む植物の特徴とアブラムシの生態
アブラムシが好む野菜とその理由
アブラムシが好む花とその理由
アブラムシはどこにいる?見つけ方のコツ
アブラムシはどこからくる?発生源を知ろう
アブラムシが好む植物の植物への影響とは
アブラムシが好む野菜とその理由
アブラムシは特定の野菜に集まりやすい傾向があります。特に葉がやわらかく、栄養分を豊富に含む野菜が好まれます。
多くのアブラムシは植物の葉や茎に針のような口を差し込んで、内部にある「師管(しかん)」と呼ばれる部分から栄養を吸い取ります。
このとき、植物内にアミノ酸が多く含まれていると、アブラムシにとっては格好の餌場になります。とくに窒素分の多い肥料を与えられた野菜は、アミノ酸の濃度が高まりやすく、それがアブラムシを引き寄せる原因になります。
具体的には、エダマメ・ダイコン・カブ・オクラ・トマト・ホウレンソウ・キャベツ・ピーマン・ブロッコリー・レタスなどが挙げられます。これらの野菜は、いずれも家庭菜園で人気があり、アブラムシの発生源になりやすいのが特徴です。
▼ベランダ菜園で虫が付きにくい野菜について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください▼ ※本ページはプロモーションが含まれています。 虫がつきにくい野菜って本当にあるの? 「ベランダ菜園を始めたいけれど、虫が湧くのが心配…」「野菜は育てたいけど、気持ち悪い虫は出来れば見たくない!!」この ... 続きを見る

ベランダ菜園で虫がつかない&つきにくい野菜13選
一方で、これらの野菜がすべて同じように被害にあうわけではありません。育て方や肥料の量、季節や気候によってもアブラムシのつき方は異なります。特に春から初夏にかけては、新芽が多く出る時期なので、注意が必要です。
このように、野菜の種類だけでなく、育て方によってもアブラムシの被害を受けやすくなることを理解しておくことが大切です。
| 野菜の名前 | アブラムシが好む理由 | 対策のポイント |
|---|---|---|
| エダマメ | 葉が柔らかく、栄養豊富 | 窒素肥料の過剰を避ける、防虫ネットを使用 |
| ダイコン | 葉や茎にアブラムシがつきやすい | 定期的な観察、早期発見と駆除 |
| カブ | 葉が柔らかく、アブラムシの餌場になりやすい | 風通しを良くする、黄色い粘着シートを使用 |
| オクラ | 成長期の柔らかい葉に注意 | 肥料のバランスを考慮、テントウムシなどの天敵を利用 |
| トマト | 窒素分の多い肥料でアブラムシが集まりやすい | 肥料の種類と量に注意、シルバーマルチを使用 |
| ホウレンソウ | 葉が柔らかく、アブラムシの栄養源になる | 収穫時期を調整、コンパニオンプランツを植える |
| キャベツ | 葉の巻き込み部分にアブラムシが隠れやすい | 葉の裏側も確認、薬剤散布は最小限に |
| ピーマン | 新芽や柔らかい葉にアブラムシがつきやすい | 成長期の観察を密にする、自然由来の忌避剤を使用 |
| ブロッコリー | 花蕾や葉にアブラムシがつきやすい | 収穫時期を逃さない、株間を適切に取る |
| レタス | 葉が柔らかく、アブラムシの食害を受けやすい | 防虫ネットを使用、定期的な水やりで生育を促進 |
ポイント
- アブラムシは、葉が柔らかく栄養価の高い野菜を好む
- 窒素分の多い肥料はアブラムシを寄せ付ける原因となる
- 育て方や季節、気候によってアブラムシのつきやすさは変わる
- 早期発見と適切な対策が重要
アブラムシが好む花とその理由
アブラムシは野菜だけでなく、観賞用の花にもよくつきます。とくに花の新芽やつぼみに集まりやすいのが特徴です。
その理由としては、開花前後の植物はエネルギーを多く消費し、葉や茎に栄養分が集中しているためです。アブラムシはそうした栄養豊富な部分を好んで狙い、花の成長を妨げてしまいます。
好まれやすい花には、バラ・チューリップ・ユリ・ペチュニア・スイレン・サルビア・シキンカラマツなどがあり、これらはどれも装飾性が高く、ガーデニングで人気の高い植物です。特にバラはアブラムシの被害が多く、定期的なチェックと対策が欠かせません。
また、室内に置かれることの多い鉢植えの花も油断はできません。外から侵入してきたアブラムシが、ベランダや窓際の花に定着することがあるからです。
注意点として、花に農薬を使用する際は、開花中の使用が難しいものもあるため、事前に使用方法をよく確認する必要があります。
このように、花もアブラムシの標的になるため、観賞用だからと油断せず、こまめに状態を観察することが重要です。
| 花の名前 | アブラムシが好む理由 | 対策のポイント |
|---|---|---|
| バラ | 新芽やつぼみに栄養分が集中しやすい | 定期的な観察、早期発見と駆除、薬剤散布(開花中は注意) |
| チューリップ | 成長期の柔らかい葉やつぼみを好む | 風通しを良くする、黄色い粘着シートを使用 |
| ユリ | つぼみや葉にアブラムシがつきやすい | 肥料のバランスを考慮、テントウムシなどの天敵を利用 |
| ペチュニア | 柔らかい新芽やつぼみが食害されやすい | 成長期の観察を密にする、自然由来の忌避剤を使用 |
| スイレン | 葉やつぼみにアブラムシがつきやすい | 定期的な水やりで生育を促進、薬剤散布は最小限に |
| サルビア | 新芽やつぼみにアブラムシが集まりやすい | 株間を適切に取る、防虫ネットを使用 |
| シキンカラマツ | 葉やつぼみがアブラムシの栄養源になる | 収穫時期を調整、コンパニオンプランツを植える |
ポイント
- アブラムシは、開花前後の栄養が集中した新芽やつぼみを好む
- 観賞用の花も油断せず、こまめな観察が重要
- 農薬を使用する際は、開花中の使用に注意が必要
- 早期発見と適切な対策が重要
アブラムシはどこにいる?見つけ方のコツ

アブラムシは非常に小さく、気づかないうちに植物へついていることが多い害虫です。見つけにくい場所に潜むため、発見にはちょっとしたコツが必要です。
まず注目すべきは、新芽や葉の裏側です。アブラムシは柔らかくて栄養価の高い部分を好むため、葉の表面よりも裏側に密集しているケースがよくあります。
また、つぼみの根元や若い茎にも集まりやすく、白っぽい斑点やベタつきが見えたら要注意です。これはアブラムシの排せつ物「甘露(かんろ)」によるもので、アリが集まっている場合もサインの一つです。
見つけるタイミングとしては、朝方や夕方など日差しが和らぐ時間帯がおすすめです。光の加減で体が反射して見えやすくなります。特に気温が20〜25度程度になる春と秋は活発に活動するため、注意して観察しましょう。
このように、葉の裏や新芽など、目に見えにくい部分を意識的にチェックすることが、早期発見のポイントです。
アブラムシはどこからやってくる?発生源を知ろう
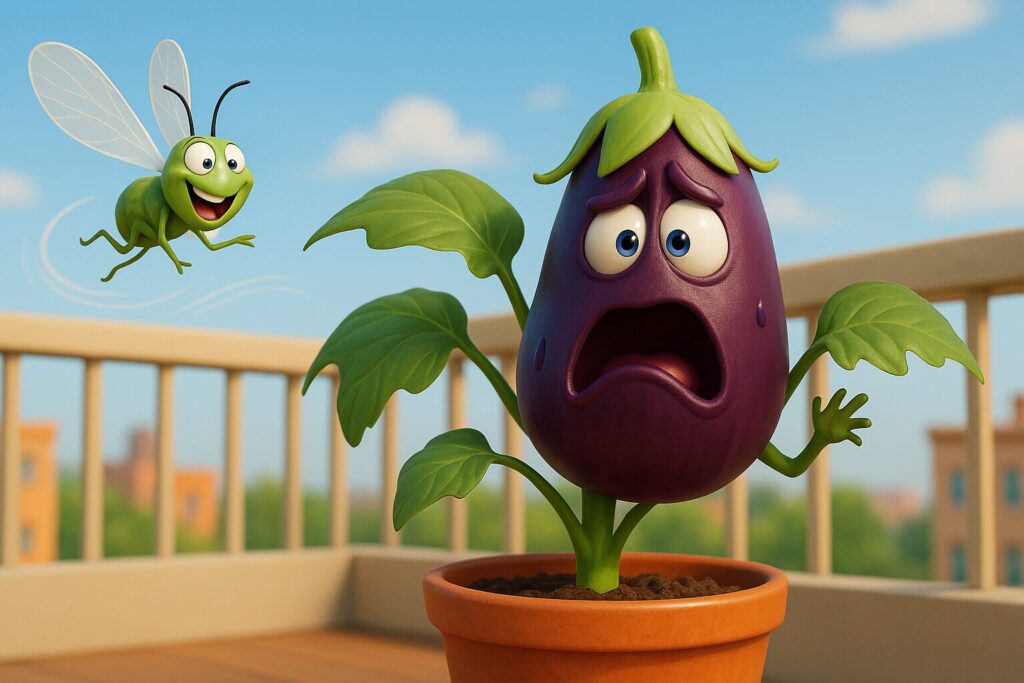
アブラムシは自然界に広く存在しており、気づかないうちに庭やベランダに侵入してきます。特定の発生源を知っておくと、事前の予防対策がしやすくなります。
主な侵入経路としては、風に乗って飛んでくる「有翅型(ゆうしかた)」と呼ばれる羽を持つ個体が挙げられます。これらは植物を求めて空を移動し、新たな寄生場所を探します。
また、すでにアブラムシがついている苗や切り花を購入した場合、気づかずに持ち込んでしまうケースも少なくありません。
さらに、アリがアブラムシを運ぶこともあります。アリはアブラムシの排せつ物である「甘露」を餌としており、その供給源を確保するために別の植物へアブラムシを移動させることがあります。
▼蟻がアブラムシを運ぶ様子▼
このような経路を知っておくと、新しい苗を購入した際には持ち込む前にしっかり確認する、風通しをよくして侵入しにくくするなど、具体的な対策が立てやすくなります。
発生をゼロにすることは難しいですが、こうした注意を日常的に意識することで被害の拡大を防ぐことができます。
アブラムシが好む植物への影響とは
アブラムシが植物に与える影響は見た目の被害だけにとどまりません。生育そのものを阻害する要因となるため、早めの対処が欠かせません。
まず、アブラムシは植物の茎や葉に口針を刺して養分を吸い取ります。これにより、植物は成長に必要な栄養を奪われてしまい、葉がしおれたり、黄色く変色したりする症状が見られるようになります。
特に新芽や若葉に集中してつくため、成長が止まる、実が育たないといった深刻な影響も起こります。
また、吸汁による直接的な被害だけでなく、「ウイルス病」を媒介することもあります。アブラムシがすでに感染している植物の汁を吸い、その後別の植物に移動して再び吸汁することで、ウイルスを拡散させてしまうのです。
これは一度発症すると治療が難しく、最終的には株ごと処分しなければならないケースもあります。
さらに、アブラムシの排せつ物である「甘露」が葉や茎の表面に残ると、それを栄養源に「すす病」という黒いカビが発生することがあります。見た目が悪くなるだけでなく、光合成の妨げになり、植物の健康をさらに損ねてしまいます。
このように、アブラムシの被害は単なる虫害にとどまらず、植物全体の活力を奪う深刻な問題です。小さな虫だからといって油断せず、日ごろからこまめな観察と早めの対処が大切です。
| 被害の種類 | 影響内容 | 結果・問題点 |
|---|---|---|
| 吸汁(茎・葉) | 植物の養分を吸い取る | ・葉がしおれる ・黄色く変色する ・全体の成長が遅れる |
| 新芽・若葉への集中 | 成長点に集まりやすい | ・新芽の成長停止 ・実が育たない |
| ウイルス病の媒介 | 感染植物からウイルスを拡散 | ・発症すると治療困難 ・株ごとの処分が必要なことも |
| 甘露の排出 | 葉や茎に蜜状の排せつ物を残す | ・すす病(黒カビ)発生 ・光合成の妨げ ・見た目も悪化 |
アブラムシが好む植物の対策と駆除方法

アブラムシの大量発生を防ぐ予防策は?
アブラムシが嫌う植物で防除効果を期待
アブラムシが死滅する温度とは?
駆除にコーヒーは使えるの?
駆除が簡単な方法とは?
アブラムシの発生予防に有効な方法
アブラムシ対策におすすめの薬剤とは
アブラムシの大量発生を防ぐ予防策は?
アブラムシの大量発生を防ぐためには、日常的な管理と予防策の積み重ねが重要です。特に春から初夏にかけては繁殖スピードが非常に早いため、気づいたときには大発生しているというケースも少なくありません。
まず、植物の育て方を見直すことが大切です。窒素分の多い肥料を多用すると、葉がやわらかくなり、アブラムシにとって格好の餌となります。肥料は過不足なくバランスよく与え、過剰施肥にならないよう注意しましょう。
さらに、風通しをよくするための間引きや剪定も有効です。アブラムシは湿度が高くて風の通りにくい環境を好むため、密集した葉の中で繁殖しやすくなります。これを防ぐには、定期的に植物の状態をチェックし、蒸れを避ける工夫が必要です。
また、こまめな観察も欠かせません。葉の裏や茎の付け根など、目立たない場所に小さなコロニーを作ることがあるため、週に一度は植物全体を観察し、少数のうちに取り除くことが肝心です。
最後に、アブラムシを引き寄せないための環境づくりもポイントになります。雑草をそのままにしておくと、そこを拠点にしてアブラムシが植物に移動してくることがあるため、周囲の管理も忘れないようにしましょう。
| 対策項目 | 内容 | 理由・効果 |
|---|---|---|
| 肥料の見直し | 窒素分を控えめにし、バランスの良い施肥を心がける | 柔らかい葉ができにくくなり、アブラムシが寄りつきにくくなる |
| 剪定・間引き | 風通しを良くし、葉が密集しないようにする | 湿度を下げて、アブラムシの繁殖を防ぐ |
| こまめな観察 | 週に一度、葉裏や茎元をチェック | 早期発見・早期除去で大発生を防げる |
| 雑草の管理 | 周囲の雑草を定期的に除去 | アブラムシの拠点となる雑草を排除し、被害拡大を防ぐ |
アブラムシが嫌う植物で防除効果を期待
アブラムシの予防には、忌避効果のある植物を上手に取り入れる方法も有効です。特定の植物にはアブラムシが寄りつきにくい性質があり、これを利用することで防除効果が期待できます。
代表的な植物には、ネギやニンニク、チャイブなどのネギ属があります。これらは独特のにおいを放つため、アブラムシを遠ざけるとされています。
また、ハーブ類ではミントやバジル、ローズマリーなども効果があるとされ、家庭菜園やプランターの周囲に植えるだけでも一定の予防効果があります。
ただし、これらの植物だけで完全にアブラムシを防げるわけではありません。あくまで「寄りつきにくくする」程度のものであるため、ほかの対策とあわせて活用するのが望ましいでしょう。
また、アブラムシが嫌う植物を使う際は、栽培環境にも配慮が必要です。混植する際には、それぞれの植物の育成条件(日当たりや水やりなど)に差があるため、相性を考慮して配置することが重要になります。
このように、アブラムシが嫌う植物を上手に活用することで、農薬に頼らずナチュラルな防除が可能になります。育てる楽しさを保ちながら、虫害の少ない環境づくりを目指しましょう。
| 忌避植物の種類 | 具体例 | 防除の仕組み・効果 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| ネギ属 | ネギ、ニンニク、チャイブ | 独特なにおいでアブラムシを遠ざける | ほかの植物と混植する場合、育成条件の相性に注意 |
| ハーブ類 | ミント、バジル、ローズマリー | 香り成分に忌避効果がある | あくまで「予防」目的、単独での完全防除は不可 |
| 活用のコツ | 家庭菜園の周囲に植える・プランターで併用 | アブラムシの寄りつきを抑制 | 日当たり・水やり条件を考慮して配置 |
アブラムシが死滅する温度とは?
アブラムシは比較的低温にも耐える害虫ですが、一定以上の高温になると生存できなくなります。その「限界温度」を知っておくことで、自然条件や対策の一つとして活用することが可能です。
おおむね40〜45℃以上になると、アブラムシは死滅すると言われています。ただし、この温度は短時間であってもアブラムシにとっては致命的であり、継続的な高温状態が続けばさらに効果は高まります。
この特徴を利用して、ビニールハウスなどでは「高温処理」と呼ばれる方法を行うことがあります。密閉した空間内の温度を意図的に上げることで、アブラムシを物理的に死滅させるというやり方です。
▼害虫の高温処理方法について詳しく知りたい方はこちらの記事を参照ください。▼
害虫の温度処理で効果的な防除を紹介---株式会社アグリクリニック研究所 大谷ファーム
ただし植物側も高温に弱いため、タイミングと温度管理には細心の注意が必要です。
一方で、真夏の直射日光によって葉の表面温度が上がることでも、アブラムシにとって過酷な環境となります。ただし、野外の植物においては日陰や葉の裏に逃げ込むことで高温を回避するケースもあるため、過信は禁物です。
このように、アブラムシはある程度の高温には耐えられますが、極端な温度には弱い一面もあります。環境を活かしつつ、ほかの対策と併用することが効果的です。
駆除にコーヒーは使えるの?
コーヒーを使ったアブラムシの駆除は、一部の園芸愛好家の間で知られている自然対策の一つです。しかし、科学的な観点から見ると、その効果は限定的であることが分かっています。
現在のところ、アブラムシの主要な駆除方法としてコーヒーの有効性を裏付ける科学的証拠は十分ではありません。
実際、ある研究では、コーヒーを散布したキュウリと散布していないキュウリの間で、アブラムシの密度に有意な差が認められなかったと報告されています。
また、農林水産省も「コーヒー(抽出液)の薬効・安全性に関する情報収集の結果について」という資料の中で、コーヒーをアブラムシの駆除に用いることについて、実用的な効果は確認されていないと明言しています。
このように、コーヒーの使用には逸話的な報告が多く存在する一方で、科学的な検証では効果を支持する結果は得られていません。コーヒーを用いた駆除はあくまでも「補助的な手段」としてとらえたほうがよいでしょう。
また、コーヒーの濃度や使用頻度によっては、植物の葉にダメージを与えたり、異臭の原因になったりするリスクもあります。
特に、コーヒーだけに頼った対策ではアブラムシの個体数を十分に抑制できず、結果的に植物が深刻な被害を受けるおそれがあります。
アブラムシの防除には、物理的除去や植物由来の安全な薬剤など、より確実性の高い方法と併用することが望ましいと言えるでしょう。コーヒーを使う場合でも、実験的に一部の葉に試すなど、慎重な運用を心がけることが大切です。
アブラムシの駆除が簡単な方法とは?
アブラムシの駆除は、必ずしも専門的な薬剤を使わなくても可能です。ここでは、家庭でも手軽にできる方法をいくつか紹介します。どれも身近な道具で実践できるため、初心者の方にもおすすめです。
手で取り除く方法
最もシンプルな方法は、アブラムシを直接手で取り除くことです。発見したアブラムシを指や爪楊枝、綿棒などを使って軽く取り除きます。葉が密集している部分や裏側に隠れていることが多いため、丁寧に確認しましょう。
ただし、大量発生している場合は時間がかかるため、早期発見がカギとなります。小規模な被害であれば、手での駆除は非常に有効です。
粘着テープで貼り付ける方法
セロハンテープやガムテープなどの粘着テープを使うのも効果的です。粘着面をアブラムシがいる部分に軽く押し当て、アブラムシをくっつけて取り除きます。
この方法は手が汚れにくく、小さなお子さんと一緒に作業する際にも便利です。ただし、粘着力が強いテープを使ったり、強く押しすぎると植物を傷つけてしまいますので注意しましょう。
水で洗い流す方法
ホースやスプレーボトルを使って水でアブラムシを洗い流す方法もあります。葉の裏側を重点的に狙い、水圧をやや強めにして吹き飛ばすようにしましょう。
この方法は植物に負担をかけにくく、繰り返し使うことができます。ただし、再び戻ってくる可能性もあるため、定期的にチェックすることが大切です。
油せっけん水スプレーを使う方法
市販のスプレーを使いたくない方には、**家庭で作れる「油せっけん水スプレー」**がおすすめです。作り方は以下の通りです。
【レシピ】
水:500ml
台所用中性洗剤(無香料):小さじ1
食用油(サラダ油など):小さじ1
この材料をスプレーボトルに入れてよく混ぜ、アブラムシに向けて噴射します。せっけんと油がアブラムシの呼吸を妨げて駆除する仕組みです。
ただし、繊細な植物には刺激が強い場合があるため、まずは一部に試してから全体に使うようにしてください。
アブラムシの天敵を利用する方法
自然の力を借りる方法として、アブラムシの天敵を活用する手もあります。特に有名なのが、てんとう虫やヒラタアブの幼虫です。これらの昆虫はアブラムシを餌として食べてくれるため、農薬に頼らず駆除が可能です。
家庭菜園の場合は、てんとう虫が来やすい環境を作ったり、園芸店で購入して放す方法もあります。ただし、飛んでいってしまうこともあるため、持続性にはやや注意が必要です。
オーガニック殺虫スプレーを使う方法
最近では、天然由来の成分を使用したオーガニック殺虫スプレーも市販されています。ニームオイルやカリ石けんなどが主成分となっており、植物や人に対して優しい処方です。
使用の際は、パッケージに記載された使用量や散布間隔を守りましょう。アブラムシが発生しやすい時期に定期的に使うことで、予防と駆除の両面で効果が期待できます。
アブラムシの発生予防に有効な方法
アブラムシを発生させないためには、日頃からの予防対策が重要です。特別な農薬を使わなくても、ちょっとした工夫で被害を防ぐことができます。ここでは、家庭菜園やガーデニング初心者にもできる7つの予防法を紹介します。
窒素成分の多い肥料を控える
窒素分の多い肥料は、植物の成長を促進する一方で、アブラムシが好む柔らかい新芽を増やす原因にもなります。そのため、肥料を使うときは、**バランスの取れた成分(N-P-K)**のものを選ぶのがポイントです。
特に春先や梅雨の時期は成長が早いため、肥料の量を控えめに調整しましょう。肥料袋に記載された推奨量を守ることが大切です。
反射テープやアルミホイルで視覚的に防ぐ
アブラムシは光の反射を嫌う傾向があります。そのため、銀色の反射テープやアルミホイルを使った予防が効果的です。植物の周囲にテープを張る、または地面にアルミホイルを敷くだけで、アブラムシの飛来を減らすことができます。
風で揺れるテープは特に効果が高いため、支柱に結んで植物の周囲を囲う方法がおすすめです。
定期的な剪定で風通しを良くする
葉が混み合ってくると、アブラムシにとって居心地の良い環境になります。そこで、定期的に不要な葉や枝を剪定して、風通しと日当たりを改善しましょう。
特に下葉や混み合った部分はアブラムシの温床になりやすいため、こまめなチェックと手入れが予防につながります。
蟻を駆除してアブラムシの温存を防ぐ
アリはアブラムシが分泌する甘い「蜜」を好み、アブラムシを守る行動をとります。そのため、アリの出入りを見つけたら早めに駆除することが肝心です。
アリの通り道に防蟻剤をまいたり、鉢の脚に水を張ったトレイを敷いたりすることで侵入を防げます。アブラムシとアリはセットで管理する意識が大切です。
ハーブを植えて忌避効果を狙う
アブラムシは一部の香りの強い植物を嫌う傾向があります。特に、ミント、バジル、チャイブ、レモングラスなどのハーブは防虫効果が高いとされています。
メインの植物の周囲にこうしたハーブを植えることで、アブラムシの飛来を抑えることができます。見た目も華やかになり、収穫して料理にも使えるため、一石二鳥の対策です。
唐辛子漬けのアルコールスプレーを散布
天然素材を使った自家製スプレーも効果的です。唐辛子をアルコールに漬け込んだスプレーは、アブラムシの忌避に一定の効果があると言われています。
【作り方】
唐辛子(乾燥可)10本程度を細かく刻む
消毒用エタノール200mlに1〜2日漬け込む
漉してスプレーボトルに入れ、水で2〜3倍に薄めて使用
散布する際は、葉の表裏にまんべんなく噴霧してください。ただし、葉が弱る可能性もあるため、まずは少量で試しましょう。
防虫シートや粘着テープを設置する
物理的にアブラムシを防ぐ方法として、防虫ネットや粘着テープの設置もおすすめです。苗を植え付けた直後や春先など、アブラムシが活発になる前に使うと効果が高まります。
防虫ネットは風通しがよく、植物を覆っても育成に支障が出にくいタイプを選ぶと扱いやすいです。黄色の粘着テープはアブラムシを誘引するため、鉢や支柱に設置すると予防に役立ちます。
このように、アブラムシの発生を未然に防ぐ方法は多岐にわたります。どれも身近な道具や植物を使った対策なので、無理なく始められる点が魅力です。いくつかを組み合わせることで、より効果的にアブラムシから植物を守ることができるでしょう。
アブラムシ対策におすすめの薬剤とは
アブラムシの被害が広がってしまった場合は、市販の薬剤を使うことで効果的に対処できます。しかし薬剤の種類は多く、それぞれに特徴があるため、植物の種類や育成環境に合わせた選び方が重要です。
ここでは、初心者にも扱いやすく、安全性にも配慮された代表的なアブラムシ用薬剤を紹介します。
有機JAS対応の天然成分系薬剤
農薬に不安を感じる方や、無農薬栽培を目指している方には、有機JAS認証を受けた天然成分系の薬剤がおすすめです。代表的なものには、ピレトリン(除虫菊由来成分)や、なたね油由来のオイルスプレーがあります。
これらは植物や土壌への影響が少なく、小さなお子様やペットがいる家庭でも比較的安心して使用できます。使用の際は、葉の表と裏にまんべんなくスプレーすることが効果を高めるポイントです。
浸透移行性タイプの化学薬剤
被害が深刻な場合や即効性を求める場合には、浸透移行性のある化学薬剤が有効です。このタイプは、植物に吸収されて内部にとどまり、アブラムシが吸汁した際に駆除するしくみです。
一般家庭用には、「オルトラン液剤」や「ベニカXファインスプレー」などがよく使われています。成分は異なりますが、どちらもアブラムシを含む複数の害虫に効果があります。
ただし、使用頻度や希釈倍率を守らないと薬害を起こすことがあるため、必ずラベルの使用方法に従って正しく使いましょう。
予防にもなる植物保護スプレー
アブラムシが寄りつきにくい環境を作る「予防用スプレー」も便利です。たとえば、天然のニームオイルを主成分とした製品は、アブラムシの繁殖を抑える働きがあるとされています。
ニームオイルは、成虫だけでなく卵や幼虫の発育を妨げる作用があるため、継続的に散布することで繁殖サイクルを断つことができます。
使用時の注意点
どの薬剤を使う場合も、いきなり全体に散布せず、まずは一部の葉でテストしてから使用することが大切です。また、花が咲く前や実がなる直前は避け、風のない日中を選んで使うようにしてください。
なお、薬剤を併用する際は、成分が重複しないように注意し、連続使用は避けるようにしましょう。アブラムシに薬剤耐性がついてしまう可能性があるためです。
このように、アブラムシ対策に使える薬剤にはさまざまな種類があります。植物の種類や被害の程度、自分の育成スタイルに合わせて適切な薬剤を選ぶことが、効果的で安全な駆除につながります。
アブラムシ 好む植物とその対策を総まとめ
柔らかく栄養豊富な葉を持つ植物にアブラムシが集まりやすい
エダマメやトマトなどの家庭菜園野菜が特に狙われやすい
バラやチューリップなどの観賞用の花も好まれる
窒素分の多い肥料を使うとアブラムシの発生が促進される
新芽や葉の裏側に潜みやすく、早期発見には細かな観察が重要
羽のあるアブラムシは風に乗って遠くから飛来する
購入苗やアリの移動がアブラムシ侵入のきっかけになる
被害が進行すると植物の生育が著しく悪化する
ウイルス病やすす病など二次被害の原因にもなり得る
剪定や通気性の確保が大量発生の防止につながる
ネギ類やハーブなどの忌避植物で発生を抑制できる
コーヒーは科学的根拠に乏しく補助的な対策にとどまる
手作業や水流による物理的な駆除も効果的な手段である
天敵のてんとう虫やヒラタアブを利用した駆除も有効
被害が深刻な場合は浸透移行性薬剤を正しく使用する

